|
Photo by Lewis Ngugi on Unsplash Javaは1990年代にサン・マイクロシステムズ(以下サン)が開発、公開したプログラミング言語である。 ちょうどそのタイミングで1996年、私はサンに転職した。 担当した職務は、Javaとほぼ同時に市場へ投入された大型UNIXサーバで小売業界での汎用機市場を奪い取ること、そしてクライアント側を席巻していたマイクロソフトの牙城をJavaで切り崩すことだった。 当時Javaの最大の売り文句は「コードを書き直したり、コンパイルをし直す必要がなく、全てのプラットフォームで稼働する」という点にあった。 折しも小売業界独特のクライアントであるPOS端末は、ほぼ100%、マイクロソフトのWindowsが搭載されており、独占市場であるが故、POS一台あたりに占めるWindowsのコストは結構な高さの比率だった。 そこをJavaとLinuxで置き換えればかなりのコスト・セービングになるはずだと考えたのである。 また、POSの周辺装置であるスキャナーやドロワーなどのデバイス・ドライバーや、アプリケーション・ソフトを開発するために標準化されたAPIが「OLE POS」として提供されていた。 これらはあくまでもWindowsをプラットフォームとすることに限定されていたため、Windowsを切り崩すためのJavaの標準化が必要だった。 サン入社翌年の1997年、アメリカでJavaPOS committeeが組織された。 メンバーにはサンの他、POSメーカーとしてIBMやNCR、ユーザーとしてシアーズやホーム・デポなどが参加し、会合はアトランタのNCR、ラーレーのIBM、パロ・アルトのサンのオフィスで持ち回りで行われた。 アメリカでのJavaPOS committee発足からおよそ半年後、日本でもJavaPOS研究会を設立することになり、まず最初のメンバーとして、アメリカで参加いただいていたIBMやNCRなどにお声がけした。 しかしなにしろ日本のサーバ市場では完全に競合相手である。 よく話を聞いていただいたものだし、参加をいただけたものだ。 次に狙ったのは国産のPOSベンダーと、ユーザーである小売業のシステム部門だった。 小売業の方々の参加は「ユーザーの声を反映する」という建前のために必要だったし、「こういう方々がコミットしてるんですよ」と世の中に示すという営業的な本音のうえでさらに必要だった。 こちらも百貨店、専門店、コンビニエンスストアの各業態から代表的な企業に快く参加いただくことができた。 当時の関係者の方々には深く感謝するしかない。 さてここから日米で歩調を併せて、各周辺機器ごとのAPI策定と標準化ドキュメント作成の作業が始まった。 全部で20あった周辺機器をそれぞれ各POSベンダーに担当を割り振らせていただき、700ページを超える「Programming Guide」として形になったのは、POS業界を挙げての努力の賜物である。 蛇足ながら私自身も序章や用語集などを執筆させていただいた。 なお現在でもWebサイトが残っており、2001年の日本語最終版v1.5がダウンロードできるようになっている。 標準化が策定された次の作業は、実際の製品化である。 サン自身はPOSを製造しているわけではないため、POSベンダーに製造してもらい、それを小売業に導入してもらうための「仕掛け」が必要だった。 そこで考えたのが、毎年3月に開催される小売業向けのIT展示会「リテールテック」で実務を兼ねたデモを行う作戦である。 敢えて展示ブースではなく、飲食の物販を行っている某ファーストフードチェーンにお願いし、メンバーの各社が開発したJavaPOSマシンを使っていただいた。 これは思いのほか評判がよかった。 この後のJavaPOSであるが、全米小売業協会(NRF)が主体となって、OLE POSとJavaPOSの上位レイヤーに当たるUnifiedPOSが策定されることになった。 言い換えると、UnifiedPOSで策定された標準をWindowsにマッピングしたものがOLE POS、JavaにマッピングするとJavaPOSという位置づけになった。 この直後の2001年に私はサンを退職したので、JavaPOSに直接関わったのはここまでである。 サンを退職した2001年以降、ITのプラットフォームは激変した。
多くのエンタープライズ・アプリケーションは汎用機からUNIXサーバへ移行したが、それが今度はx86サーバ(いわゆるPCサーバ)とLinuxの組み合わせに雪崩を打って移り始めた。 残念ながらサンはUNIXによる成功体験が大きすぎたためであろう、Linux市場への移行に後れを取った。 まさに「イノベーションのジレンマ」のサンプルのような事態だ。 結局2009年、サンはオラクルに買収されることになってしまった。 それ以来、Javaのパテントもオラクルである。 POSもまた大きく変化を遂げた。 ちょうどPC市場がスマホやタブレットの直撃を受けたように、PCをベースにしてすべての周辺機器が一塊になったターミナル型のPOSマシンは、タブレット型に置き換えられていく。 タブレットと周辺機器は直接接続されるのではなく、ネットワークを介して通信する形態になったため、標準化もまたUnifiedPOSに加えてWeb Service POSが制定される。 この流れは今後、IoTの一形態になっていくのだろう。 こうした中でPOSベンダーの顔ぶれも変わってしまった。 2012年にはIBMがPOS事業を東芝テックに売却して事業撤退。 またDSS研究所の調査によると、平成27年度のPOSベンダー別シェアは、東芝テック、NECプラットフォームズ、富士通フロンテックの3社で80%近くを占め、続くシャープと寺岡精工以外のベンダーはほぼ壊滅してしまった状態である。 そしてJavaは組み込み機器からサーバに至るまで幅広く利用されるようになったものの、近年頻繁に脆弱性が発見されるようになってしまい、ブラウザのプラグインからの削除を推奨されるような状況である。 投入初期に先頭に立って旗振り役を務めた立場としては返す返すも残念だ。
0 コメント
返信を残す |
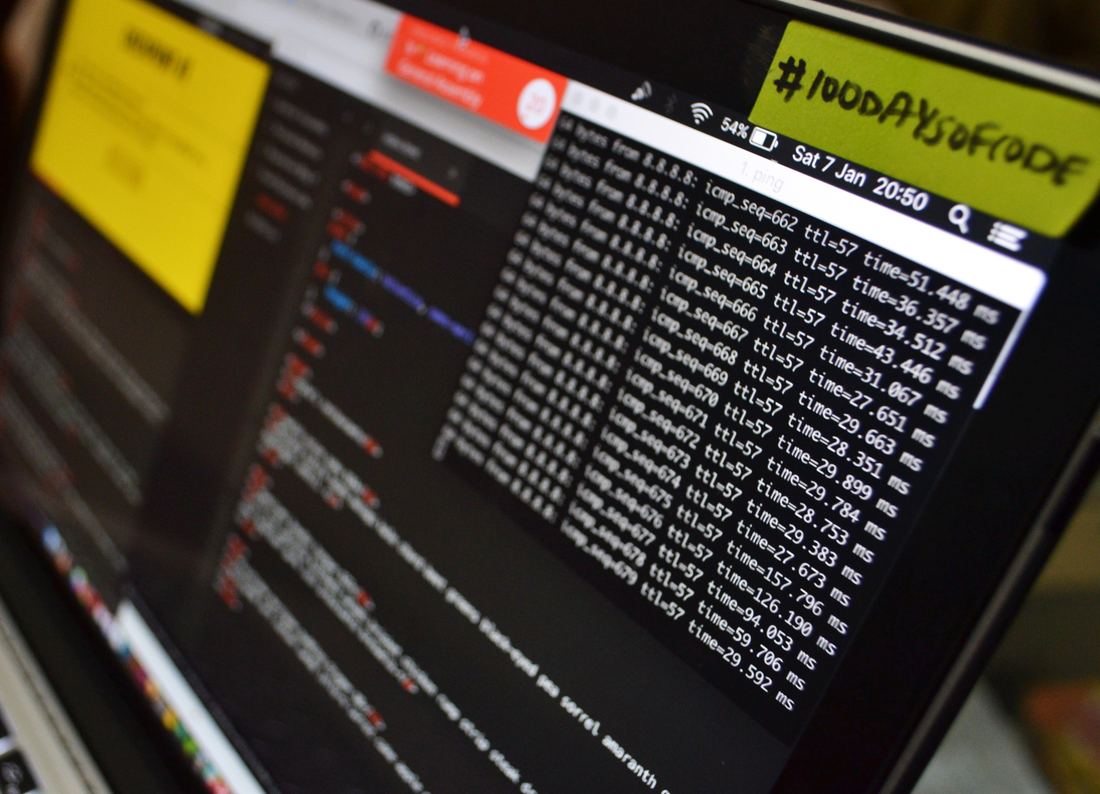
 RSSフィード
RSSフィード